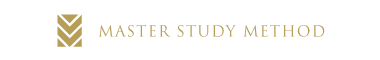この記事は書きかけです。思いついたことを箇条書きの状態にしています。
・ジョブズ
・日本記憶力チャンピオン
記憶力世界・日本チャンピオンは誰としてひとり、ブドウ糖による記憶力のアップを言っていない。少しくらい効果を感じても良いのではないか?試験の前にブドウ糖の補給をすると書くはずではないだろうか?
・勉強をするときは他の刺激を取り除く
・勉強をしているとき、ブドウ糖の消費が著しくなるのを確認したのだろうか?根拠は?もし、ブドウ糖を大量に必要とするのであれば、まともに勉強をしている学生達は全員やせているはずです。
・毎日、朝食を食べる人の実験からきたものではないか。この実験は人間性や生活状態を無視している。「毎日、朝食を食べたほうが成績が良い」という実験データは学校の先生や脳科学者の中で一般的なものとなっている。だからこそ、それを知っている学生やご両親も多いのではないでしょうか?そんな中、毎日、朝食をまじめに食べている人は、普段、真面目な生活を送っている人かもしれない。反対にこの情報を知っているにも関わらず、朝食を食べずに学校へ行く子どもや親はどんな考え方をしているのでしょうか?「勉強なんてどうでもいい」くらい思っているかもしれません。この実験では、直接、朝食と記憶の関係性を証明するにはあまりにもお粗末過ぎるといわざるを得ない。せめて、全く、同じ人で実験をするべきだろう。
・おなかが減ったとき「ああ、記憶が薄れてきた~。」「さっき何してたかなぁ~。」と経験した人はいるのだろうか?
・餓死寸前の人は記憶喪失になっているだろうか?むしろ、鮮明に覚えている。感情が働くからだ。生命の危機に瀕しても、脳へのエネルギー供給だけは最優先で必ず行われる。そして、生命維持において記憶する機能は最後まで切り捨てられる事はないということは証明されているはずだ。ブドウ糖だろうとたんぱく質であろうと脂質であろうとエネルギーを確保する。すべてが使えると思っていいのではないか?
・少なくとも脳は記憶だけを担当しているわけではありません。生命維持の為に、消化・吸収や体温の維持、血液の循環、免疫機能など人類最高の頭脳をもってしても再現できないようなことを常にやっているのです。ブドウ糖が不足しただけで、脳の機能が低下していてはあっという間に死んでしまうでしょう。また、ブドウ糖の不足で都合のいいように記憶の機能だけを切り捨てたりもしません。頭を使うというのは、それらの複雑な機能に比べれば、大したことではありません。私の見解では頭を使ったり、記憶したりすることは人間にとってそれほどの負担にはならないのです。
・「お腹すいたから、ブドウ糖の補給をしなきゃ!」と心配しないでください。「死にませんし、記憶力も無くなりません。」むしろ、勉強中に余計な事を考えているのに気付きましょう。その考えは、勉強の助けになるどころか、勉強の中断を促すだけなのです。
・もし、このことが信じられないなら、命がけで挑戦してみましょう(自己責任で)。何も食べず、勉強をし続けてください。いずれお腹が空いて、限界が訪れるでしょう。その時、暗記術を使っても記憶術を使っても、何も覚えられない状態になるのか分かるはずです。それでも、腑に落ちないなら、さらに餓死状態へ追い込みましょう。生命の危機状態になるまで。あなたはそこで分かるはずです。この命がけの実験を含めて前後の記憶がないか。それとも、この実験を鮮明に覚えているか。私は実験をしたことだけでなく、何を勉強したかまで、生涯忘れられない記憶になると確信しています。そして、二度とやらないでしょう。
・そして、毎日普通に食事をしていれば、そんな状況に置かれる事はありません。ブドウ糖の不足が記憶力を
・「脳の栄養にブドウ糖を使っている(これは事実かもしれないが・・・。)」だから、「勉強のときにブドウ糖を摂取しましょう」というのは脳科学者の飯の種にしているだけではないかと思うのです。
・脳科学者が言っていることをそのまま鵜呑みにしてしてはいけません。私たち人間は権威ある人間の言葉をすぐに信じてしまう傾向にあります。様々な知識を取り入れ多面的に物事を捉え、自分が正しいと思えることを信じてやりぬきましょう。