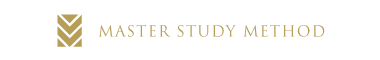私たちは普段から、音の関連付けを利用して、記憶しているものです。それを証明するためにマジカルナンバー7をもう一度、覚えてみてください。
3548128
覚えられましたか?当然、同じ順番で何度も回転させて、覚えたことと思います。そして、「連続性」のリンクとは別に「音」のリンクも利用しているはずです。実際に発声したかどうかには関わらず、「サン、ゴ、ヨン、ハチ、イチ、ニ、ハチ」と音に変換させていると思います。これをせずに、形だけを焼き付けて覚えようとしてもなかなか覚えられないのです。(写真の様に脳に記憶を焼き付ける方法が出来る人もいるみたいですが・・・)
この簡単なテストをするだけでも、いかに音とリンクさせて記憶するのがどれほど大切なのか理解して頂けたのではないかと思います。
さらに音のリンクは「旋律(リズム)」を利用することで、より強力なものになります。リズムが良ければよいほど規則性が強くなり、強いリンクを作ることができます。
このため九九では、リズムの良い段と悪い段で格段に覚えやすかったり、覚えにくかったりするわけです。
また、語呂合わせや歌などもリズムを利用している良い例です。これら2つはストーリー法の良さも兼ねていますので、より記憶しやすいのではないでしょうか。
音のリンクとリズムを利用することは情報を次々に引き出すのにかなり強力な方法と言えるでしょう。
「音のリンク」を使う場合のポイントは次の2点です。
まず、1つ目は音をリンクさせるために実際に声に出さなくても良いという事です。
実際に声に出すと、噛んだり、流暢に話せなくて速度が犠牲になる場合があります。また、一般的に頭の中だけで音をアウトプットするほうが、速度はかなり速いものになります。そして、この方法は実際に声に出して発声するよりも疲れませんし、学校の授業中などさまざまな状況でも使えるでしょう。
上級者になると本を速読するので、音に変換するよりも早く文字を読んでいきます。そして、重要部分のみ音に変換し速度に差をつけることができる様になります。このような方法も、また、改めて速読、読書力の記事で紹介していきます。
2つ目は、読めなくても何が何でも音に変換すると言う事です。
英語で発音の分からないものは発音を調べるべきですが、辞書が無い場合にはローマ字読みでも構いませんので、音とリンクをさせるようにしましょう。また、これは英単語だけでなく、漢字などでも言えることです。
もちろん正しい読み方を調べるのがベストですが、当て字などで読めない場合はそのまま読むのもありです。間違った読みで音とリンクさせているだけでも漢字の形だけで覚えようとするよりは遥かに早く長期的に覚えることが出来ます。
僕は蒲公英を「ぼこうえい」と読んでいた時期があります。(※一応、和名では正解)これは「たんぽぽ」と読むのですが、もし間違っていたとしても恥ずかしさと相まって感情と結び付けられて、記憶はより一層強くなりますし、読みではなく、漢字を書く場合には、むしろ和名のほうが漢字を引き出しやすくなります。これは英単語も同様で、ローマ字読みのほうがスペルを正しく思い出せる場合が多々あります。
このように英単語や漢字は臨機応変に正しい発音とは別にローマ字や和音を利用し音だけで2つのリンクを持たせるとより記憶を強く保持することが出来るのです。
ただし、読みが実際に問われることもあるので、間違った読み方はリンクを強くし過ぎないように注意しなければなりません。ベストは「ぼこうえい」と書いて「たんぽぽ」と読むと両方覚えておくのが一番良い方法です。勉強が出来る人なら普通のことかもしれません。勉強をしているとこのような例は無数にあります。
しかしながら、音のリンクを複数持つというのは良い点ばかりではありません。もし、2つのリンクを作ろうとすれば単純に覚えなければいけない量は2倍になるのですからそれだけ大変であることには変わりありません。音のリンクに限らず、「量が増える」と言うのは記憶術の最大の欠点の一つでしたね。
ですので、英語単語などはスペルが覚えにくい場合や発音が特殊な場合。漢字であれば、当て字が使われている場合などに限定してうまく利用するべきです。
音のリンクは非常に利用しやすく、勉強において「利用のしやすさ」「頻度」「速度」「記憶への効果」を総評すると圧倒的に最強のリンクだと考えています。
だからこそ、どんな学習の時もまずは「音」に変換しましょう。
「発音の仕方が分からない。」「読み方が分からない。」
そんな場合であっても、間違ってもいいので予測を立てて「音に変える」のです。
また、正しい「音」としっかり結びつけるためにも、学校の登下校や食事、風呂場などでリスニングをしたり、実際に覚えたいカテゴライズしたチャンクを頭の中で何度も高速に回転させていきましょう。これらは全て、音と記憶の性質を生かした超効率的な勉強法なのです。