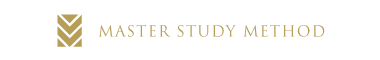今回は「物事の核(核心)」「記憶の幹」について深く話をしていきたいと思います。
同じ関連性の記憶を整理して入れていくと、記憶同士が結びついてきて、一つに繋がるようになります。「全ての物には必ず『核』が有る(byサボ)」と言いますが、それが見えてくるんですね。この時、物事の理解が飛躍的に高まり、記憶もまた強固なものとなります。そして、面白い事に、この記憶の核の部分を作る事が出来れば、周辺情報はその核に吸い寄せられるように関連付けをしてくれます。ですので、周辺情報はより一層、覚えやすくなるのです。
「核心」となる知識や情報と言うのは存在しますが、その記憶だけでは絶対に「記憶の幹」を作る事はできません。その情報単体ではどんなに質の高い情報も単なる「カケラ」。何の意味も持たないのです。核心となる情報もまた、初めから存在しているものではなく、学習者は集めた知識同士をリンクさせる事で初めて核心の情報として生きてくるのです。
核心となる情報とは「なぜ、そうなるのか?」理屈の部分を構成する情報です。
教えるということはこの核心の情報を繋げるという行為そのものと言えるかもしれません。「あ、分かった」と感じるのは核心にある情報とあらたな情報が結びついたときに感じる感覚。そうやって、核心の部分がより強く大きく成長していくのです。しっかりと核心が育ったものそれを「記憶の幹」と表現しています。
記憶は木に喩えられます。
「メモリーツリー」これは本当に記憶の性質をよく表している言葉だと思います。「記憶の幹」が出来ると、その関連した情報は、核に引き寄せられてメモリーツリーの一部になります。これは記憶術の極意①で説明した「既存情報とリンクさせる」と同じ事が起こるためです。
ひとたび「記憶の幹」が出来てしまえば、それはアンテナのような役割を果たし、関連した情報を結び付けていってくれます。メモリーツリーは「記憶の幹」ができると急速に大きく成長していくのです。
深く理解した情報においては、核心となる情報が多く無数のリンクで「記憶の幹」が出来ており、長期に渡って記憶する事ができます。そのためには、記憶の性質をしっかり理解し、様々なタイプのリンクを結びつける必要があります。
「記憶の幹」を構成する記憶であろうと「葉や枝、茎、根」を構成するような記憶であろうとも、きちんと記憶術を学び「カテゴライズ」や「連続性」「旋律」「規則性」「感情」などを利用すれば、より無数の強いリンクで結びつける事が出来ます。それを暗記術で高速回転し、リンクを何度も何度も辿れば理解はより深くなり記憶も強固なものとなっていきます。
ここで学んだみなさんには、是非、探究心や好奇心をもってメモリーツリーを構成するたくさんの「記憶のカケラ」を集めてください。そして、さまざまな記憶術で記憶同士を結びつけ、暗記術によって高速にリンクを巡る旅をしてもらいたいと思います。そうすればきっと、あなたの記憶の宇宙に、がっちりとした幹からたくさんの枝を伸ばし葉をつける巨大なメモリーツリーが根付くでしょう。
<もっと考察>メモリーツリーは葉や茎、根すべてから栄養を得て成長する
木は太陽の光を浴びて、葉や茎、根から得た養分を吸収し大きくなります。これはメモリーツリーにも言えることなのです。核心部分を構成しない「応用問題」や「周辺情報」もまた、核心部分の結びつきを強くするのです。それは、その問題を考えるとき核心部分の情報を利用し考え、答えを導くためなのです。
メモリーツリーを大きくするには当然、核心部分の情報も必要ですが、それだけではただの枯れ木になります。その核心となる記憶を利用して、何かを考えたり解決したりしなければ、やがてそれは朽ちていくだけでしょう。「記憶の幹」を強くし、葉を実らせ大きくするにはさまざまな関連した記憶が必要なのです。
「標準は基礎を兼ねる」
これは僕の尊敬する吉永賢一先生の言葉です。核の部分ばかりにとらわれることなく、自分自身でよく考えより効率的にメモリーツリーを育てていってください。
<もっと考察>「記憶の幹」を育てるのは「探究心」や「好奇心」。なければ、戦略的に作りにいけ!
勉強が出来る子はこの「記憶の幹」を真っ先に作りに行く。その感性や感覚が鋭いといえます。そして、その幹に枝や葉を実らせていく。だからこそ、理解が深く記憶も早い。そして、いつまでも忘れません。
この「記憶の幹」を真っ先に作りに行こうとするのは「探究心や好奇心」に依存するところも大きいかもしれません。なぜ?という「疑問の種」を見逃さず、深く追い求めていく姿勢がその種を成長させるのでしょう。
勉強が出来ない子はその教科、分野における「探究心」や「好奇心」をあまり持っていません。なぜ?と言う「疑問の種」に対して、自らの頭を積極的に使って解決しようとしないのです。そういった姿勢では「記憶の幹」はなかなか立派なものには育ちません。
そういう子どもに、学校のようにちょっと学習しては別の教科。ちょっと学習しては別の教科。これでは忘却を挟み、速度が下がり、非効率な学習の繰り返し。いつになっても「記憶の幹」は育たないでしょう。テスト前に、(記憶の)枝や葉っぱを拾い集め、その場しのぎをする羽目になるのです。そんな記憶など長期には残りません。だからこそ、勉強が出来ない人ほど戦略が必要になります。同じ方法では、理解度もスピードも違うので太刀打ちできないのです。
「分野を徹底的に絞る」というのが重要です。
「記憶の幹」を体感する方法として数学なら「計算」を選ぶのも一つの手です。難易度が低く、誰もが成功しやすいからです。
計算だけに絞ることによって理解が深まり、速度が増しているその時間を利用するのです。その速度で一気に駆け抜ける。私の経験では早い子なら中学3年分の計算を1ヶ月で終わらせたこともありますし、小学3年生が2ヶ月で6年分の計算を終わらせることが出来ました。どちらも、宿題無しの週2回2時間。まだ、伝授していないテクニック(インターリーブなど)を利用していますが、この実績に近いことをかなりの割合で岳伸塾の生徒達は実現しています。
「記憶の幹」が出来ると、新たな記憶を得るスピード、問題を解いていくスピードが格段に速くなります。これが驚くほどに速いのです。2倍、3倍・・・時として数十倍。にもなるでしょう。
そんな速度で駆け抜けていくのです。勉強が分からず、1問1問止まっている状態を思い浮かべてください。これではどんなに勉強しても追いつく事はできないのです。
「記憶の幹」が出来ていないのにも関わらず、他の教科、他の教科・・・。さらに、分からないまま進んでいく。残念ながら、勉強が出来ない子にとってはこれが学校の教育です。だからこそ、それとは反対の発想を持たなければなりません。勉強が出来ないなら他の全ての教科を捨ててでも、1教科のメモリーツリーを作り上げる。僕ならそうします。
「教科を絞れ、分野を絞れ。」そして、一点突破勉強法で駆け抜けろ!
詳しくは「一点突破勉強法」を参照してください。