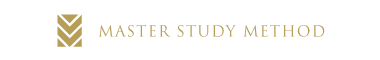情報は整理して、記憶していくと記憶同士が関連付けされた状態で頭の中に入っていきます。
それも、可能な限り細かく分類わけしてチャンク化(小さな塊)する事によって、関連付けはより強固
なものとなります。これを「カテゴライズ」と言います。
記憶術を行う場合必ず、情報を整理して、カテゴライズしていることが分かります。九九もまた、一桁×一桁の計算だけを集め、さらにその中で1~9の段と分けられています。(カテゴライズ)、そして、その情報を順番に並べてそれを何回も反復する事で覚えていくはずです。
前回の動画で紹介した頻度を表す副詞として、「always(いつも)、often(よく、たびたび)、usually(ふつう)、sometimes(ときどき)」(中学の範囲)をカテゴライズして覚えましたね。多くの参考書ではおそらくこのようにまとめて、記載されています。
しかし、ほとんどの学生はしっかりとカテゴライズしたチャンク(塊)同士の関連づけが弱く、たった4つの語句しかないのにも関わらずもれなく全て記憶を引き出す事ができないのではないでしょうか。当塾の生徒たちはカテゴライズに加えて、必ず順番通りに引き出していきます。
このカテゴライズしたチャンクの関連付けを強くするには、いくつかポイントがあります。
1つ目は、カテゴライズされた情報の一部が出てきたら、そのチャンク内の情報全てを順番にアウトプットしていくことです。先ほどの頻度を表す副詞を例に挙げると、教科書でofenが出てきたら、「always(オールウェイズ)、often(オーフン)、usually(ユージュアリィ)、sometimes(サムタイムズ)」とアウトプットをするルールを決め、完全に覚えるまで絶対に守ることです。
2つ目は、これらのアウトプットをするカテゴライズのチャンクを何個が持っておき、気が向いたときにアウトプットをすることも大切です。特に白紙復元(何も見なくてもアウトプットが行える)が出来るチャンクを持っていれば、トイレやお風呂などで教材が無くてもアウトプットをすると言ったことも出来ます。こういうちょっとした努力をしなければ、次第に情報がバラバラになり、記憶同士の関連付けが弱くなっていきます。
情報を単体で記憶していくと、アウトプットをする際に他の情報へのリンクが無いため、万が一忘れたときに思い出せる可能性が低くなってしまうのです。
カテゴライズを意識することは、記憶力を強めるだけに留まりません。
カテゴライズは「理解を深める」ために、非常に重要な役割を果たします。
ちょっと、極端な話をしますが、英語から1問、数学から1問、国語から1問、理科から1問、社会から1問ずつ問題を解いていったとします。果たして理解は深まっていくでしょうか?これでは、記憶がバラバラになり、整理されていきませんよね?そう、理解を深めるためにはこの反対をやるべきなのです。
理解を深めるためには、徹底的にカテゴライズし、同じ種類のものを集めようとする意識を持たなければなりません。特定の分野をカテゴライズし何往復もしていれば、いずれ「物事の核」が見えてくるようになります。その核を中心に記憶が吸い寄せられるように、塊(チャンク)が出来ていきます。こういった記憶のチャンクは意味記憶となり、非常に強い記憶として保存されるのです。
カテゴライズ(分類わけ)は、受験勉強で最も大切な過去問を解いていく際にも非常に強力な武器になります。
過去問でのカテゴライズはまた、別の記事で取り上げたいと思います。
勉強をする際は、必ずカテゴライズを意識するようにしましょう。自分自身でカテゴライズを行い、知識を整理する事が出来れば、理解が深まり記憶はより一層引き出しやすくなります。
<もっと考察 「因果関係」とつなげる>
勉強法の本を読んでいて、リンクの作り方が「凄い!」と思ったので紹介します。
「東大流 頭が良くなる記憶法」(著:吉永 賢一) 「因果関係」とつなげるより、一部引用
【地理第1回】 山脈
夕張山地、奥羽山脈、越後山脈、木曽山脈、中国山地、筑紫山地・・・
【地理第2回】 川
石狩川、利根川、信濃川、熊野川、吉野川、太田川、筑後川・・・
【地理第3回】 平野
石狩平野、庄内平野、関東平野、大阪平野、広島平野、筑紫平野・・・しかし、山脈なら山脈、川なら川、平野なら平野と分けて覚えても、なかなか覚えられません。なぜなら、こうした分類は、人間にとっては「機械的分類」であり、覚えにくいからです。
私たちが覚えなければならないことは、しばしばこうやって「機械的分類」でまとめられています。だから、そのまま覚えようとすると、大変な労力がかかってしまいます。そこで、覚えなければいけないことを「機械的分類」から「自然的分類」へまとめ直していくことが必要になります。
・・・中略・・・
湿気のある風が「山」にあたる → その結果、雲ができて「山」に雨が降る → 雨は低いところに向かって流れはじめ、「川」をつくる → 「川」は土砂を運びながら流れ、河口に「平野」をつくる → 「平野」のあるところに「街」ができる
この因果関係を使って「奥羽山脈→北上川→仙台平野→石巻」「越後山脈→利根川→関東平野→銚子」「四国山脈→吉野川→徳島平野→徳島」というグループをつくり、ひとまとまりで覚えていくのです。
このリンクはしっかりと意味のあるカテゴライズされており、自然法則にしたがって順序まで与えられています。
こんな事、どこかで習わないとなかなか自分で思いつくものではありませんね。さすがは吉永賢一先生!この書籍には他にもたくさんのリンクのつくり方が載っていますので、興味のある方は、一度、読んでみてください。